カメラでの撮影の失敗は、ピンぼけと手ブレが大半です。
どうして手ブレが起きるのか、その原因を調べて、どうすれば手ブレが起こらないのかを考えてみましょう。
| 1.手ブレ写真とはなにか |
|
そもそも手ブレ写真とは、ピントが合っているのにも関わらず、シャッターを切るときにカメラが動かしてしまった状態で撮影した写真です。すると撮像素子に入る光もぶれて入るのでブレた画像になってしまいます。 しかし、カメラを完全に固定してあればさほど問題になることはないのですが、手持ちで撮影する場合はどんなに気をつけてもシャッターを切る際にわずかにカメラが動いてしまうので、たえず手ブレが起きているとも言えます。 しかし実際にはいつも問題になるような手ブレが起きているわけではありません。 なぜかというと例えばシャッタースピードが1/100秒程度であれば手ブレによる振動よりも速いので、手ブレにはならないのです。ですから光が充分にある環境であればよほどヘマをしない限り手ブレが起きません。 ではどんなときに手ブレが起きるのでしょうか。 |
| 2.どうして手ブレが起きるのか |
| 3.手ブレ補正機構はどこまで有効なのか |
| 最近では手ブレ補正機構を搭載したカメラが一般的となっています。 これは、カメラ本体に搭載されている場合と、デジタル一眼レフカメラの交換用レンズに搭載されている場合があります。 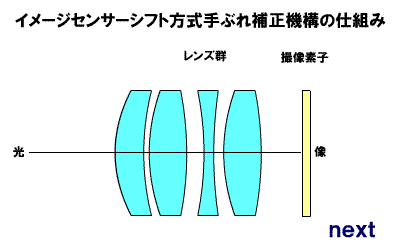 手ぶれ補正機構にはデジタルカメラ等における記録時に受光素子から受け取った画像データから計算を行い補正をかける電子式と、物理的に光軸を調整する光学式が存在します。 手ぶれ補正機構にはデジタルカメラ等における記録時に受光素子から受け取った画像データから計算を行い補正をかける電子式と、物理的に光軸を調整する光学式が存在します。デジタルカメラでは、主に光学式手ブレ補正方式が採用されています。これにもいくつかの方式がありますが、ここではレンズシフト方式とイメージセンサーシフト方式を紹介しておきます。 レンズシフト方式は、レンズ内に振動ジャイロ機構を備えた補正レンズを組み込み、ブレを打ち消す方向に補正レンズを動かす事によって光軸を補正します。 右図は、レンズシフト方式の手ブレ補正機構の仕組みをFLASHで表現したものです。手ブレが発生したときに補正レンズを移動することでイメージセンサーに到達する光の動きを補正し、手ブレを軽減させる仕組みです。 レンズシフト方式のデメリットは、光学的に設計がとても難しいということです。また、手ブレ補正の際に厳密に光学部分だけに着目すると、色収差が大きくなるなど細かい部分で光学性能が劣化してしまうという点も不利な点です。また、振動ジャイロやレンズを動かす機構を組み込まなければいけませんから、手ブレ補正機構が大きくなってしまい、レンズが大きく、重くなりがちです。
もう一つのイメージセンサーシフト方式は、振動ジャイロ機構で手ブレを感知すると、イメージセンサー(撮像素子)を手ブレに応じてシフトして光軸を補正する方式です。 下図はイメージセンサーシフト方式の手ブレ補正機構の仕組みをFLASHで表現したものです。手ブレが発生したときにイメージセンサーを移動することでイメージセンサーに到達する光軸を補正し、手ブレを軽減させる仕組みです。 この方式だとカメラ本体に補正機構を組み込むので、レンズ自体に補正レンズを組み込む必要が無く、デジタル一眼レフカメラであれば補正機構を搭載しないレンズであってもそのまま利用する事が可能であることと、レンズ系は何らいじらないので手ブレ補正の作動によって画質の低下がないというメリットがあります。 ただし、コンパクトデジカメであれば撮像素子が小さいので駆動するにも消費電力が小さくてすみますが、デジタル一眼レフのように大きな撮像素子を搭載している場合は、消費電力が大きくなることが考えられることと、撮像素子を振動させることで寿命が短くなる可能性もあります。ですから、現時点ではどちらの方式で手ブレ補正機構を搭載させるかはメーカーによって考え方が異なるようでマチマチの対応になっているようです。 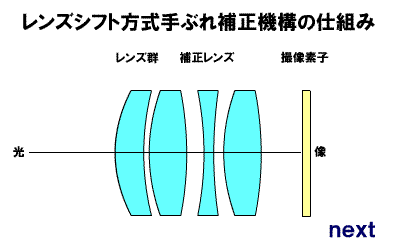 例えばCANONやNIKONのデジタル一眼レフの場合は、レンズ側に手ブレ補正機能を搭載しています。 例えばCANONやNIKONのデジタル一眼レフの場合は、レンズ側に手ブレ補正機能を搭載しています。デジタル一眼レフの二大メーカーがレンズ側に手ブレ補正機能を搭載させているということは、やはりその方式の方がメリットが大きいと判断していると考えた方が良いのではないかと思います。ただし、オリンパスのデジタル一眼レフは本体側に手ブレ補正機能を搭載しています。 いずれにしても焦点距離の長いレンズを使用する場合は、三脚を使わないのであればまず必須の機能ですので、手ブレ補正機構を搭載したカメラを購入するべきです。 私の所有するカメラではDMC-FZ30がレンズシフト方式の手ブレ補正機構を搭載しています。 このカメラは、35mm換算で420mmもの焦点距離を持っている高倍率ズームレンズを搭載していますので、手ブレ補正機構は必須と言えます。 実際にこのカメラの最大望遠を手持ちで撮影してみると、手ブレを感じさせないクリアな画像が得られますので、手ブレ補正の威力を知ることができます。 右の写真は、真立ダムを最大望遠で撮影したものですが、手ブレを感じさせない画像になっています。ただし、長焦点レンズでは威力を発揮する手ブレ補正ですが、暗いところではあまり効果があるとは言えないようです。 ですから暗いところではあまり手ブレ補正を過信するのは禁物ですので注意が必要です。 |
| 4.手ブレを防ぐには |
まず考えられる方法としてはISO感度を上げることが考えられます。 これによりシャッタースピードが速くなりますので手ブレを起こす可能性が低くなります。 ただし、ISO感度を上げすぎると画質が低下してしまうので、あまりむやみに感度を上げるのは考えものです。 これについてはカメラの性能にもよるので一概には言えませんが、最新機種やデジタル一眼レフはかなりISO感度を上げても画質の低下が小さいので、そのような場合はISO感度を上げて試してみるのも良いでしょう。 具体的にはISO800程度までなら何とか見られる画像になるようですが、それ以上は画質が低下してしまうので、やめておいた方が良いでしょう。 またシャッターを切るときにシャッターを切ってすぐに指を離すとそのショックで手ブレを起こすので注意が必要です。 しかしいずれにしても三脚なしで暗いところでの撮影では望遠で撮影するのは手ブレを発生させやすくなるので、あまりズーム動作はしない方が無難と言えます。 しかしこのような暗い環境では、ピントもうまく合わないことも考えられますが、マニュアルフォーカスではピントを合わせるのはかなり困難ですから、オートフォーカスでがんばってみましょう。 またフラッシュを使用するかどうかですが、被写体までの距離が短くてフラッシュの光が届くようであれば、フラッシュを使用することにやぶさかではありませんが、フラッシュの光が届かないようであれば、フラッシュは使用せずに対処した方が良いでしょう。フラッシュを炊いてしまうとどうしてもシャッタースピードが速くなるので、手ブレは起こりにくくなりますが光が届かないと暗い画像になってしまうのです。 |
||||||||||||||


